5.視空間の構造
5.1 大きさと距離の知覚モデルとしてのパースペクティブ空間
視空間のモデルとしてのパースペクティブ空間はそのパースペクティブ特性に基づいて構築された。このモデルは視空間の対象のアングル、大きさ、奥行距離を予測する。Erkelens(16)によれば、物理空間からパースペクティブ空間への変換関係は図58のように表される。図の(a)は観察者(右端)からある奥行距離に2次元の物理グリッド(青色表示)を提示すると、パースペクティブ空間ではそれはある奥行位置に定位され、それと観察者の結ぶ線分はすべて消失点(VP)に収束する(橙色表示)ことを示す。図の(b)には物理グリッドを時計回りに30°中心軸に回転した場合、図の(c)には消失点が観察者の背後にある場合のパースペクティブ空間をそれぞれ示す。図59には、パースペクティブ空間における奥行距離と大きさについて示し、(a)には、物理対象(青色表示)が観察者(右端のドット)から物理距離Zpに位置し、消失点が距離VPにあれば、その大きさSv(赤色表示)は奥行距離Zvに視えることを示す。図の(b)は標準と比較の2刺激がある場合で、ある標準対象Spsが物理奥行距離Zpsに、比較対象Spcが奥行距離Zpcにあるとき、パースペクティブ空間では消失点がVPにあれば後方の対象のの大きさはSvs、前方のそれはSvcとなることを示す。
この時、物理空間と視空間における奥行距離の関係は次式で表される。
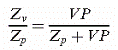 -------- (1)
-------- (1)
大きさは距離と同じように次式で規定できる。
![]() -------- (2)
-------- (2)
標準と比較の2刺激を提示した場合の物理的大きさと視覚的大きさの関係は次式のようになる。
![]() -------- (3)
-------- (3)
標準刺激に対する比較刺激の大きさは次式のようになる。
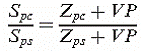 -------- (4)
-------- (4)
図60はVPを変数としたときの視えの奥行距離と視えの大きさの変化をグラフに表したものである。図の(a)には、式(1)にもとづき、パラメータはVPにとり物理距離(Zp)を変えたときの知覚距離(Zv)の変化を示す。もしVPが無限(青色表示)であれば、物理距離と知覚距離は一致し、もしマイナスになれば、物理的距離を過大視し、逆遠近法となる。図の(b)には 式(4)にもとづき物理距離の関数としての標準刺激(Sps)に対する比較刺激(Spc)の大きさの比の変化で、パラメータはVPである。VPが無限大(青色表示)となれば、知覚された大きさは物理距離とは無関係になり、大きさ恒常性を示す。VPがマイナスでは知覚された大きさは過大視される。VPがゼロ(0)ならば知覚された大きさは網膜に投影された大きさによって決まるので、物理距離に比例して縮小する。
このパースペクティブ理論は2つの前提のもとで成立する。一つは、視空間はユークリッド空間であるという前提である。つまり物理空間の直線は鉄路のように視空間でもその直線性を維持し、また物理空間の複数の整列した線分は視空間でも整列性を維持する。前提の二つは、対象の方向は物理空間と視空間で一致することである。
Erkelensはパースペクティブ理論をGilinsky(1951)の数学モデル、Ooi & He(2007)のモデル、ベキ関数モデル(Baird &
Wagner, 1991)、Wagnerのvector
contractionモデル(1985)、およびFoley (2004)の視空間モデルと比較し考察した。Gilinskyの数学モデルは、パースペクティブ理論とは異なる原理にもとづくが、対象までの知覚された奥行距離と大きさを導く数式は両理論とも等しい。Ooi & Heのモデルでは、地面に置かれた対象の奥行距離知覚には観察者の眼の高さおよび地面の知覚した傾きが考慮されたが、パースペクティブ理論との相違はほとんどなかった。ベキ関数モデルではパースペクティブ理論の距離判断のすべて範囲でその相違は小さいもので、ベキ関数モデルとパースペクティブ理論のどちらのモデルでも奥行距離と大きさの判断は適切に説明される。Wagnerのvector contractionモデルはランダムに提示された対象(棒刺激)間の距離判断のために提案されたもので、この種の知覚問題の範囲では妥当といえる。最後にFoley のモデルは、観察者から奥行方向の異なる2点の杭の間の距離知覚を課題としたもので、それは2点間の距離イメージの大きさと奥行距離に比例して規定されるとした。Foley のモデルとパースペクティブ理論は、奥行距離と2点間の距離知覚が同じパラメータでは規定されない点で共通するという。
このようにErkelensは、パースペクティブ理論が他の5つのモデルを統合するモデルであると主張する。
5.2 球面天体的オプティクアレー(planispheric optic array)の空間知覚
球面天体的オプティクアレー(planispheric optic array)とは、全水平線のオプティクアレーをもつメルカトル投影のことである。メルカトル図法とは、地球儀を円筒に投影したもので、地軸と円筒の芯を一致させ投影するため経線は平行直線に、緯線は経線に直交する平行直線になる。地図上の2線のなす角が地球上の角度と等しく正角性を維持するには、横方向・縦方向の拡大率を一致させる必要があるために緯線はすべて赤道と同じ長さにするので高緯度地方は実際の長さ(地球儀上の長さ)より横方向に拡大、それに応じて縦方向(経線方向)にも拡大する。
最近で全周囲カメラが安価に発売され、利用が高まっている。Koenderink & van Doorn(21)は、そのようなカメラで撮影した写真の空間配置を理解して用いているかについてしらべた。実験ではまず、図61にしめすように、ある地点の中央に全周囲カメラを配置し、その周りの4つのコーナーに一人ずつ人を立たせ、コーナーのいずれかに頭と胴体を向け、同時に片手を伸ばして指さしを行い、それを撮影し、全周囲写真が作成された(図62)。ここでは、水平線は十全だが、垂直方向は±74°の表示に留まった。25名の成人被験者に、各コーナーの指示者の指示する方向が異なる全周囲写真をプリントアウトして渡し、指示者(A、B、C、D)が他の指示者の誰を指さしているかあるいは誰も指していないか(図63の7種類)をアンケート方式で記入させた。
その結果、誰かを指し示すと答えた反応数は0.29にとどまり、約2/3は誰も指し示さないという結果となった。被験者の間の一致度(一致すれば+1、しなければ-1)をみると、これも0.18にとどまった。また、正しい指さし対象を選んだ割合は29%、間違った対象を選択したのは2%、あとは指さし先として何も選択しなかったのは69%に上った。
これらの結果から、被験者は指さし対象そのものを選択できないことが示された。図64に示したように、物理的空間(右図)を全周囲撮影した空間は左図のメルカトル空間となる。この場合、図65に示したように、4つのコーナーにいるA、B、C、Dの各人に左側の人あるいは右側の人を選択させると、2つのケースを除いて特定のひとりに収斂できないことがわかる。このようなメルカトルの知覚空間では誰も正確に他の誰かを指さしできないと考えられる。
方向の異なる空間表象が視覚と運動を導く場合
従来、ものを掴むような運動を起こす場合、ターゲットの位置や大きさを知覚し、この情報にもとづいて運動の計画を立てると考えられてきた。しかし、視覚情報に一致しない運動が起きる場合があり、この場合には視覚情報は運動に対して独立した過程として働く((Bridgeman et al. 1981,Burr et al.2001, Goodale et al.1991)。一般に、視覚経路には2通りあり、ひとつは腹側経路、他は背側経路である。前者は対象が何であるかを同定し、後者は対象に対する感覚から運動への変換を起こす(Goodale & Milner, 1992; Milner & Goodale, 2008)。
Lisi & Cavanagh(25)は、このような知覚と運動の異なる処理過程を"Double-drift
targets"(ガボールパターンを観察者の前額に直角あるいは斜方向に動かし知覚的な位置と方向を物理的なそれより大きく異ならせる)現象を利用してしらべた。図66のAに示すように、ガボールパターン(2
cpdで100%コントラスト)を物理的に動かす方向と位置、それの知覚された方向と位置(サッケード眼球運動を指標とする)、観察者の指さした位置がそれぞれ示されている。実験では、ガボールパターン全体を観察者の右あるいは左斜方向に1.2秒で交互に往復させて動かし、その物理的運動の両端でフラッシュさせて提示する(external
motion)。サイン波形の方向は物理的運動方向に同一とすると、ガボールパターンそのものは物理的な運動方向に直角に3Hz でドリフト(drift)して視え(internal
motion)、したがってdouble-drift条件となり、その知覚的運動方向は観察者の正中線方向になる(図のA) 。被験者にはターゲットであるガボールパターンを観察させ、フラッシュした時点での視えの方向をキーボードで答えさせた。また、ターゲットの運動軌道の眼球運動測定のために、視野の中心の注視点を凝視させ、次いで運動するターゲットを提示し、どちらかの端で1回フラッシュし、そのときのサッケードを測定した。さらに、ターゲットの位置を指さしで測定するために(pointing)、運動するターゲットの両端での位置をスクリーンをタッチさせる通常の方法、あるいは半透明になるシャッターゴーグルを装着し開閉させて自分の指が視えない条件(open-loop pointing)で測定した。
その結果、サッケードによるターゲットの位置はターゲットの物理的位置と同等になることを示したが、指さしによるターゲットのpointingは大きくサッケードの位置とは異なることが示された。この指さし(pointing)の位置がサッケードと異なることは観察者の手が視えない事態でも確認された。これはサッケードの眼球運動による視覚情報処理は他の運動とは異なることを示唆した。
このことから、サッケードの眼球運動は時間的に最近接のごく短時間のシグナルに対応しているのに対して、指さしなど意識的な知覚と運動は時間的により長期の情報を統合して遂行されていると考えられる。
重力に基づくリファレンス(枠組)での視方向の更新
対象の視方向を規定する要因には、対象自体の方向リファレンス(対象中心要因、object-centered
reference)、観察者の頭部方向リファレンス (egocentric reference)、そして観察者の重力リファレンス (gravity direction reference)の3通りがある。もし、これらのリファレンスの一つが変われば、その正しい方向関係を維持するために前の記憶された対象の空間関係を再計算(updating)する必要がある。
Niehof et al.(28)は、視覚の空間枠組に囲まれた1本の線分の方向が、観察者の頭部方向が変わることによって垂直な空間枠組の時に記憶した線分の方向に影響するかについて検討した。もし線分の方向が重力リファレンスに基づいて記憶されれば、その記憶も変化した空間枠組によって影響されるし、また頭部運動の回転方向によってこの記憶が書き換えられれば、方向の知覚は新しい頭部位置での重力方向の変化に影響されると考えられる。この重力モデル(gravity-based model)によれば、線分方向システムの更新エラーは頭部運動それ自体によるよりは記憶から方向を読み出す時、並びに記憶に方向が記銘される時の重力フレームの主観的な歪みによると予測する。しかし、線分の方向が対象中心の座標のなかで視覚的空間枠組に関連づけられて貯蔵されれば、空間枠組が新しい方向に変わる時には、世界中心の本当の方向を正しく登録し維持するために、これらの座標の更新が必要となる。この場合、頭部の傾斜後にこの種の記憶の読み出しが起きると考えられる。
実験では、被験者の記憶された視方向が頭部の傾斜に伴ってどのように変化するかがしらべられた。図67に示したように、ディスプレーに1本の垂直あるいは傾斜線分とそれを囲む線分の四角形枠組を提示し、観察者の頭部を垂直あるいは右に傾けさせて観察させた。実験では被験者に合図を送って頭部を右に30°傾けさせ、線分枠組を左右45°の範囲のいずれかにランダムに傾斜させて提示した。種々の傾きのある線分刺激を枠組提示の後で50ms提示し、その後に枠組に類似した線分をマスク刺激としてランダムに提示した。この後、被験者には頭部を垂直にもどすように教示し、線分枠組を垂直に提示し、さらにプローブとしての線分を提示し、これが時計回りにあるいは反時計回りに傾斜して視えるかを判断させた。プローブ線分は試行の80%を垂直に、あとの20%は角度をランダムに提示した。統制実験には、頭部を右30°傾けさせ、空間枠組を左右45°の範囲内でランダムに傾斜させた事態で垂直線分の傾きを測定し、被験者の線分知覚判断能力をしらべた。
このように、被験者には頭部を傾けたままで種々に傾斜した空間枠組内の線分の方向を記憶させ、その後で頭部を垂直に戻して垂直な空間枠組内の線分の方向を記憶したそれと比較して判断させた結果、記憶試行とプローブ試行の線分方向の判断のエラーは記憶試行時の頭部傾斜とプローブ試行時の垂直な頭部の両方の事態での知覚的重力要因によって生起したことが示された。この種の判断エラーが観察者の頭部運動から直接媒介されたものではないこともあわせて明らかにされた。
これらのことから、視覚システムは線分の方向知覚を重力に基づくリファレンスに依拠し、このリファレンスは頭部運動が起きても線分の方向を記憶していると考えられる。