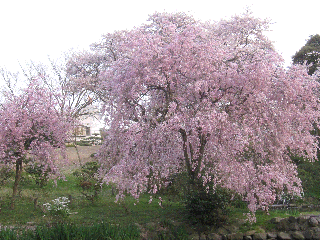
桜
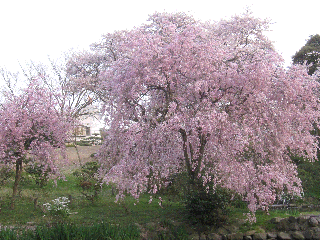
桜
まもなく桜の季節となる春分も間近い。自宅から眺められる公園の周りに植えられた桜も蕾がふくらみ、mるで濃いピンク色のベールをかけたようで、いよいよ春到来の感を深くする。歳を経ると、あと何回桜の季節を迎えられるかといった問いが心をよぎるので、いっそう桜の咲くのを待つ思いがつのる。
「散る桜 残る桜も 散る桜」
この俳句では、はらはらと散る花びらも、いまを盛んに咲いている花も時がくれば散ってしまう。ことほど左様に、死んだ人も現に生きている人もいずれは命は絶える。これが厳かな命の原理なんだと詠んでいる。
これは江戸時代後期(18世紀中頃から19世紀初め)の曹洞宗の僧侶で歌人、漢詩人、書家だった良寛の辞世と伝えられているが定かではない。この句を有名にしたのは、太平洋戦争の末期の特攻隊員、奥山道郎大尉が弟に当てた遺書のなかに「散る桜残る桜も散る桜、 兄に後続を望む」と書き残されていたからだった。
総じて、桜には生と死のイメージがまとわりつく。パッと咲き、パッと散るその姿が命の輝きとはかなさを連想させるからだ。
「さまざまのこと思い出す桜かな」
これは45歳の芭蕉の句で、自分が若き日に仕えた亡き主君との花見の宴を思い出して詠んだものと言われる。桜には誰にでもある懐かしき思い出を呼び出させるものがあるようだ。私にも花見の宴といえば、父、叔父、そして経営していた店の者たちで近所の護国神社で繰り広げられた花見の宴が忘れられない。多分、小学校2〜3年の頃だった。終戦後7〜8年たち、戦争も遠のき、世の中も落ち着いてきて大人たちは素直に満開の桜を愛で、重箱に詰めたご馳走を食し、酒を飲んで酔いしれた。
「お酒呑むな、酒呑むな、ご意見なれどヨイヨイ、 酒呑みゃ酒呑まずにいられるものですか」と大声で大人たちが歌っていたのを子供心にも楽しそうだなと、よく覚えている。
こんな感慨から、一、句
「あれこれともの思わせる桜かな」 敬鬼
2016年3月19日