今日も今日とて、男あるじは徒然草を手にわが縁の下の庵にやってきて、その一節を朗読し始めた。
「『花はさかりを、月はくまなきをのみ見るものかは。雨に対ひて月を恋ひ、たれこめて春の行方知らぬも、なほあわれに情け深し。咲きぬべきほどの梢、散りしをれたる庭などこそ見どころ多けれ』。どうだな、なかなかに趣がある見方だな」と話し出した。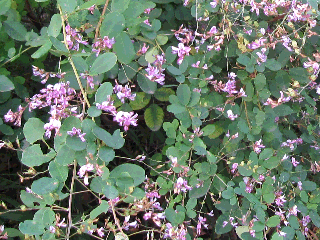 わが輩は、趣がある見方より偏屈な見方ではないのかといぶかしく思った。桜の花がこれ見よとばかりにすべての枝に花を付けているのを見るのは、気分が高揚するものだし、中天にかかり煌々と照る満月は気分を晴れ晴れとさせる。もっとも、満開といい満月といい、その時にタイミング良く出くわすことはそうそう無いだろうけれども、しかしそのときを幸運にも得れば、豪奢な時を過ごせるというものではないか。男あるじもわが輩の思っていることを察したと見えて、つぎのように反論してきた。
わが輩は、趣がある見方より偏屈な見方ではないのかといぶかしく思った。桜の花がこれ見よとばかりにすべての枝に花を付けているのを見るのは、気分が高揚するものだし、中天にかかり煌々と照る満月は気分を晴れ晴れとさせる。もっとも、満開といい満月といい、その時にタイミング良く出くわすことはそうそう無いだろうけれども、しかしそのときを幸運にも得れば、豪奢な時を過ごせるというものではないか。男あるじもわが輩の思っていることを察したと見えて、つぎのように反論してきた。
「確かに、花は盛りが見栄えがあり、欠けたるところのない月は人を感嘆させる。しかし、それらは時の流れのなかではわずかな時間、まあ一瞬といってもよい。花は散っている時間の方が長いし、月も日数をかけて欠けていく。つまり、すべてものごとが頂点にあるのは一時、一瞬のことであり、それを越してしまえば消えていく運命にある。徒然草の一三七段では、『万の事、はじめおわりこそをかしけれ。男女の情も、ひとへに逢ひ見るをばいふものかは』と述べているぞ。ここに、ものごとの極みを最高の美と讃えるのではなく、その前後のものごとの移り変わりゆく様にこそ美があるというわけだな。男と女の中も、逢えない恋、偲ぶ恋、ひとときのみで終わる恋などにこそ男女の愛の情けがある」 わが輩は、花も、月もそして男女の間などそれもこれも、ものごとの極みを見るからこそ、その後の滅びに愛惜を感じるのではないか、と眼で問うと、男あるじは、
「その見方は正しい。すべてのものごとには盛りと滅びがある。要は盛りと滅びのどちらに視点をおいて考えるかにある。兼好法師も同じ段で『彼の桟敷の前をここら行きかふ人の、見知れるがあまたあるにて知りぬ。世の人数も、さのみ多からぬこそ。この人みな失せなむのち我が身死ぬべきに定まりたりとも、ほどなく待ちつけぬべし。大きなる器に水を入れて、ほそき穴をあけたらむに、したたること少なしといふとも、怠るまなくもり行かば、やがてつきぬべし』と書いている。これは、大きな器から漏れる水が少しでも、いづれは無くなるように、知人も一人亡くなり二人亡くなりしていずれは消えて無くなる。自分もやがては同じ運命になる、との意味だな。ここには仏教の無常という教えが底流にある。無常とは、この世に生まれ出たすべてのものは常なる姿を留めることはなく一瞬のちには変化しいずれは滅してしまう、ことをいう。つまり、すべての生きとし生けるものは生々流転する定めにあり、永遠に留まることを求めてもその願いは得られないのだ。このような死生観に立つと、花は盛りではなく散るのが、我が身になぞらえて共感できることになる」と長い説教を終えた。
わが輩は、首うなだれて拝聴した。きっとわが輩の方が早くこの世を去るのであろうから、この話は身につまされるわけだ。さりとて、ひょんな事からわが輩の方が後になるかも知れない。徒然草では、『(死は)若きにもよらず、つよきにもよらず、思ひかけぬは死期なり』とあるそうだから。
「故郷も すすきと団子で 月見かな」 敬鬼